パリでのひと夏
パリで、べつべつの国からやってきた学生たちと、ひと夏を過ごす、という、まるで数年前みた「スパニッシュアパートメント」のような生活をしている。
平日は9時から16時くらいまでパリ政治学院で授業をうけ、その後は美術館によったり、パン屋やマルシェで買い物をしてキッチンでフランス料理をつくってみたり、ルームメイトたちとお酒を飲みに出て、そしてフランス語の復習をする。
フランスという国は思い描いていたそのままにうつくしい。中学校の頃に傾倒したフランス文学や傾倒したフランス映画の、あらゆるシーンをフラッシュバックさせながら、パリの街を歩くと、なんともまあ現実感を抱くことができないものだ。大学の近くにはサルトルとボーヴォワールが語り合ったカフェだったり、彼らが仲良く一緒に眠る墓地があったりするのだもの。ボリスヴィアンがトランペットを演奏していたバーや、デュラスの住んでいたアパート、ヘミングウェイ夫妻が滞在していたホテル、オスカーワイルドがなくなったホテルがあるのだもの。
ルーブル美術館や、オルセー美術館、うつくしいセーヌ川沿いの街並みをあるくとき、フランスの哲学者や文学者たちの作品をよみとくとき、西洋文化のゆたかさ、歴史、そしてなによりその美しさに圧倒されてしまう。
私はフランス趣味の母のもと、教会で育ったということもあって、西洋文化に身を浸して育ってきた。でも、こうやってあこがれた西洋の文化に身を置いてみると、自分がやはり異質な、東洋からやってきた存在だということを認識させられる。
でも、もっとこのうつくしい国にちかづきたい、そういう気持ちでいっぱいで、フランス語が思うようにつかうことができないのが、自分がどうもがいてもこの国に属していないという事実が、とてももどかしい。
それにしても、
いろんな国を移動して、いろんな国からやってきた人と話す、こんな生活がつづけられればいいのになあ。


「her/世界でひとつの彼女」は、人工知能が神になる近未来の到来を予言した物語である
20歳の誕生日に渋谷で見た、ということでわりと思い入れがあるこの作品。
英語圏でHimといえば、その意味するところはたったひとつ。キリスト教の全知全能神である。キリスト教は一神教、つまり、その神は”世界でひとつ”の存在であるために、先頭の文字はキャピタライズされ、定冠詞無しで表記されるのが通例である。
それを意識したに違いない、スパイクジョーンズ監督の映画「her/世界でひとつの彼女」の原題はHer。この作品における神、つまりHerは、人工知能であるサマンサ。「「her/世界でひとつの彼女」は、人工知能・サマンサが、HimらしからぬHer(=神)になるまでの話である。

物語は神無き時代ともいえるであろう、近未来のサンフランシスコ市が舞台である。
あらすじはこんな感じ。
そう遠くない未来のロサンゼルス。ある日セオドアが最新のAI(人工知能)型OSを起動させると、画面の奥から明るい女性の声が聞こえる。
彼女の名前はサマンサ。AIだけどユーモラスで、純真で、セクシーで、誰より人間らしい。セオドアとサマンサはすぐに仲良くなり、
夜寝る前に会話をしたり、デートをしたり、旅行をしたり・・・・・・
一緒に過ごす時間はお互いにとっていままでにないくらい新鮮で刺激的。ありえないはずの恋だったが、親友エイミーの後押しもあり、
セオドアは恋人としてサマンサと真剣に向き合うことを決意。しかし感情的で繊細な彼女は彼を次第に翻弄するようになり、
そして彼女のある計画により恋は予想外の展開へ――!
“一人(セオドア)とひとつ(サマンサ)"の恋のゆくえは果たして――?
冒頭、サマンサはセオドアを暖かく見守る、母親的存在として現れ、終盤にはSingularity(技術的特異点)を通過し、文字どおりデウス・エクス・マキナ(deus ex machina)に進化する。
デウス・エクス・マキナとは、ギリシャ語で「機械仕掛けから出てくる神」を意味し、ギリシャ悲劇の内容が解決困難な局面に陥ったとき、上方から現れる、絶対的な力を持つ存在つまり神を指す。転じて、混乱した事態を円満に収拾する便宜的な役割を指すそう。
サマンサは、アップグレードによりSingularityを経験した結果、人間理性の信仰をベースとして進化したテクノロジーによって生み出された、神なき社会における問題さえも解決する、デウス・エクス・マキナ(=機械仕掛けの神)になるのだ。
ジョーンズ監督はサマンサとセオドアの関係を描くことによって、テクノロジーが人類を超越し、神的な存在になる可能性を示唆している 。
この作品は、ハリウッドの定番ともいえるロマンティックコメディのお決まりを踏襲し、それにモダンでスタイリッシュな舞台デザインを施しながらも、根幹には<AIによる人類の超越>という全く異なったテーマをおいている。
これまでのハリウッド映画との比較を通して、デジタル社会の人間関係、人間とテクノロジーの関係性、テクノロジー、の変化について考察したいと思う。
デジタル社会の人間関係
herの世界では、人々の関係性が極度に希薄化している。人々は、デジタルテクノロジーによって支えられた、快適で、安全で、便利な社会にすっかり慣れ、他人との関係や、それによっておきるトラブルのような雑音を受け止める能力をなくしてしまっている。
1920年代、「アメリカの良き時代」に撮影された、ロマコメの古典であるキャプラの「或る夜の出来事」で描かれる社会とは対照的だ。「或る夜の出来事」の舞台となるバスが象徴的。まったく見知らぬ他人同士が隣の席に座り、話しかけ、世間話をし、歌い踊り、ときに喧嘩をする。カオスとさえもいえるような雑多さだ。でもその混沌さは、主人公のふたり、エリーとピーターの出会いを生み出す。

これはherの世界では全く見られない光景である。この近未来のロサンゼルスの、ゴミひとつない美しく整った街は、完璧な調和とデザインの上に成り立っている。街ゆく人々を見ると、だれもネクタイやベルトをしていないのに気がつくだろう。街からも、人々からも、必要のないものはすべて取り除かれているのだ。
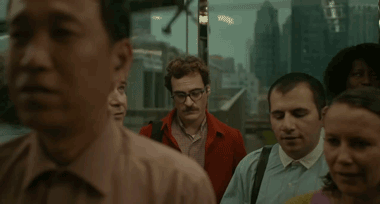
セオドアのアパートのエレベーターは、人で満杯の時も、奇妙なほどに人の交流がない。隣人であるにもかかわらず、だれも他人に話しかけない。みんな自分のデバイス(スマートフォンのようなもの)に夢中になり、独り言を言うように、自分のOSに話しかけている。「或る夜の出来事」の舞台となるバスとは正反対の光景である。
テクノロジーによって人間は安全で、快適な環境を手に入れたいっぽうで、人々は人間関係やそれが生み出すトラブルを受け止め解決する能力を失ってしまったのだ。
そんな人々の中でも代表的な存在なのがセオドアである。彼は、絶望的なほどの孤独感を抱きながらも、人と触れ合うのを怖れている。彼は人間に対して人並みはずれた興味を抱きながらも、幼馴染との離婚をしたという苦い経験のために、人と関わることを怖れているのだ。だから、テレフォンセックスで饒舌に女性を口説くことはできるのに、ブラインドデート相手の生々しい感情に触れたときには、彼はなにもできず立ちすくんでしまう。彼は他人の親密な手紙を代筆することに秀でた才能をもっているのに、最後まで前妻に手紙を書くことができない。彼はその孤独を、一日中スクリーンの前で、ゲームやテレフォンセックスをして過ごすことでなんとか誤魔化していきている。
この映画は、セオドアの描写を通し、ハイテク社会で深い孤独感を抱えながらも、人と関わることができず、テクノロジーに一時の気休めをもとめて生きる人々を風刺しているのだ。
テクノロジー観の変化
この映画はテクノロジーに対する現代の人々の価値観についても綿密に描いている。チャップリンのモダン・タイムスでは、機械=技術はガルガンチュアン的に描かれていた。工場の人に食事をさせる機械や、ベルトコンベアは、人の意に反して加速し、恐ろしい力をみせる。チャップリンにとって、機械は非人間的で、人の範疇を超えうるものであり、人から人間らしさ、人間の暖かさを奪ってしまう、脅威をもった存在だった。

herで描かれるテクノロジーは一線を画している。サマンサはただ高い知性を保持しているだけではなく、創造性、感情、思慮深さ、ユーモアなど、私たちが<人間らしさ>と捉えるようなあらゆる要素を有している。彼女がセオドアのために彼女が作った曲を彼に披露する瞬間、くだらない絵を描いて彼を笑わせる瞬間は、彼女がシンギュラリティ、つまり人間を超えた存在へと変化するプロセスをはじめた瞬間だったのだろう。
Her - The beach scene - YouTube
彼女は世界中の情報にアクセスするだけでなく、人と関わり、様々な感情を経験する中で、全知全能となっていく。彼女のシンギュラリティは、OSの総アップデートの後に完成する。このアップデートで、彼女は時間や空間に関係なく自由に動くことができるようになった。これは、彼女がセオドアや他の人間たちのように、物質的世界、つまりいつか終わりのある、限界のある世界から解き離れたことを意味する。全知全能で、そして限界をもたない。彼女とOSたちは、神といってもおかしくない存在にまで成長をしたのだ。だから彼女はセオドアの「本」、つまり彼の「世界」に住むことができない、というのだ。
別れの前に、セオドアはこれまでサマンサを愛したように他の人を愛したことがない、というと、彼女はこう答える。
“Me too. Now we know how to”
これはAIが人に愛するということを教えるという段階にまで成長した、アイロニーに満ちた描写である。
モダン・タイムスでは、テクノロジーは人が手に負えない威力をもち、人と敵対する非人間的存在として描かれていた。Herでもテクノロジーは人が手に負えない強大な存在として描かれているが、決して人と敵対していない。超人間的である。精神的なレベルで人を超越し、ほとんど神のような存在として描かれている。
ふたりの恋愛関係について
まったくバックグラウンドの異なる二人が恋に落ちる、というのはロマコメのお決まりである。「或る夜の出来事」も、上流社会を代表する、お金持ちで、未成熟な若いエリーと、労働者階級を代表する、シニカルで経験豊富な中年のピーターが、ともに旅をする中で貧しさや飢えなどの困難を乗り越え、一種父娘的な恋愛関係を築くに至る。これは1920年代、大恐慌の中社会に存在する格差が浮き彫りになったアメリカ社会に対し、個人レベルの関係で、階級の差を乗り越えることができる、というメッセージをこめたからなのではないかと(わたしは)思う。

Herにおいても、ヒーローとヒロインはまったく異なる設定である。セオドアは人間で、サマンサはコンピューターシステムである。「或る夜の出来事」と異なるのは、二人は父娘的ではなく母と息子のような恋愛関係を築くということ、そして二人のバックグラウンドの違い、つまりリアルとバーチャルは、決して乗り越えられないということである。
(つづく)
思い出はみえない
引き出しの奥には、赤と、青と、橙色と、いろんな色のビー玉たちが潜んでいる。それぞれのビー玉の中には、違った世界が広がっている。重みのあるそれを一つとりあげて、じっとのぞいてみる。最初はぼんやりとしかみえないけれど、だんだん目が慣れてくるので、もうすこし辛抱する。しだいに、東京のネオンライト、横断歩道のシマシマ、信号の赤青黄色、そして道を行き交う人々が見えてくるようになる。しばらくすると、道路にたたずむ一人の少女の後ろ姿が浮かび上がってくる。見覚えのある深い紺の制服、肩とどくくらいの黒い髪から、それが中学生のころの私であることに気がつく。
ビー玉を灯りに透かせば、明るくなって昼になり、暗いところで覗き込めば夜になる。 わたしはひたすらビー玉をあつめて、それを一日中眺めて暮らしていた。ほかにはなんにもしないで。自分の生活なんか、どうでもよくなってしまうくらいにそれらの世界が魅力的だったものだから。
という夢を昔見た。
子供のとき、ビー玉あつめに凝ったことがあった。からっとした青色のビー玉、ガーネットとレモンイエローの、まるでオレンジキャンディーみたいなビー玉、赤とイエローの金魚柄のビー玉、いろんなお気に入りのビー玉を集めていた。
ビー玉はいまでも好きで、今でもジャムの瓶につめて飾ってクローゼットの上に飾っている。ときどき意味もなく取り出しては、蛍光灯に透かしてみたり、ノートの上にならべて、そのカラフルな影をながめたり、影を混ぜ合わせて新しい色をつくってみたりもする。
映画「害虫」の、主人公のサチ子がビー玉の詰まった瓶を倒すシーンを思い出す。彼女の細い指で瓶を倒してしまうと、ビー玉は大きな音を立てて一気に流れ落ちて行く。
昔の思い出を集めて眺めてみる。
思い出のひとつひとつには色がついていて、カメラのフィルターをかけたようにぼんやりとしている。まるでビー玉をのぞいているみたいだ。私の思い出のはずなのに、そのなかにいる私を私は見下ろしている。だからもうこれは頭の中でつくられた思い出だっていうことだ。
思い出すとき、心が明るければそれははっきりときれいな思い出に見えるし、心がなんとなく暗い日は陰鬱な暗い思い出のようにうつる。喫茶店で読んだフロム、富山県の雪、寺院にたむろする猿。おでこのにきび、日焼けした黒い腕、しみ一つない曲線の美しい背中、星座をつくり出せそうな腿のほくろ。冬の公園の遊具、眠れずひとりで歩いた夜の新宿のネオンライト。赤くなった一重まぶたの目、もうそろそろジャム瓶はいっぱいになってしまうので、もう一つ新しく調達しなくちゃいけないだろう。思い出は、それ自体で完結している。ひとつひとつが短編小説みたいに、一本の映画のように独立している。心が無意識に、ひとつのお話としてしあげようとしているからだ。だからどんどん思い出は、思い出せば思い出すほど、しぜんと脚色されて、ストーリーとして美化されて、かたちがととのって、どんどん美しくなる。本当のすがたからは離れていってしまう。
鈍感さという暴力、鈍感さという救い
藤野可織さんの「爪と目」、鹿島田真希さんの「冥土めぐり」を読んだ。
両方とも芥川賞を受賞したという共通点はあるものの、この2冊は違う作者によって書かれた全く違う話。でも、鈍感さが周囲に与える影響を描いているという点では同じといえる。
「あなた」は目が悪かったので父とは眼科で出会った。やがて「わたし」とも出会う。その前からずっと、「わたし」は「あなた」のすべてを見ている――。三歳の娘と義母。父。喪われた実母――家族には少し足りない集団に横たわる嫌悪と快感を、巧緻を極めた「語り」の技法で浮かび上がらせた、美しき恐怖作(ホラー)。(新潮社)
裕福だった過去に執着する母と弟。家族から逃れたはずの奈津子だが、突然、夫が不治の病にかかる。だがそれは、奇跡のような幸運だった。夫とめぐる失われた過去への旅を描く著者最高傑作。
- (河出書房)
3歳児がその継母を語る、一貫した二人称で書かれた「爪と目」は、ぞっとするようなお話。語り手である少女は、怒りも悲しみもなく、恐ろしいほど冷静に、淡々と継母の毎日を描く。継母の一挙一動をこの上なく鋭く、そして偏執的なまでにこと細かに描写しているので、感情が徹底的に排されたこの文体からも、彼女自身が形容しがたいとてつもない憎悪を継母に抱いているということが自然と伝わってくる。
登場人物は、語り手である3歳児、その父親、そして父親が再婚した継母。継母は人を積極的に傷つける種類の人間ではない。無意識のうちに、人を傷つけているような人間だ。語り手からみれば、彼女はどこまでも鈍感である。なんとなく、という理由で結婚をし、インテリアにはまり、ものを食べ、排泄し、くらしている。語り手は無意識のうちに人のこころを踏みにじる鈍感さに強い怒りを覚え、彼女に「制裁」を下すのだ。
冥土めぐりに登場する奈津子の夫も、どこまでも鈍感な人間である。ただ、その鈍感さは、「爪と目」の継母とは違い、奈津子の救いとなっている。奈津子の母と弟はひとから平気で搾取できるような人間。金銭欲と消費欲に支配され、自分は一流の人間だと思って疑わない奈津子の母。同じく自分は特別な人間だと考えハーバード大学に進学さえすれば自分の本来の価値が行かせると夢想してやまない弟。奈津子はふたりの世界に強烈なまでの嫌悪感を抱きながらも、反抗する気力も失い、縛られたままいままでいきてきたのである。
若くして脳症を発病し、「アダルトビデオを持つことで自分が男だと思っているような」奈津子の夫太一は、彼らの悪意には全く気がつかない。彼は思考しない。彼は感じない。人間関係など感知しないのだ。だから彼の目には悪意など映らない。本来の無垢さとその障害で、社会や人間関係との完璧なまでの隔絶を獲得した太一は、奈津子の母と弟の呪縛からするすると逃れることができる。聖愚とさえいえる太一とついていくことで、奈津子はついに二人の呪縛からのがれることができるのある。
爪と目の継母と太一とは、周囲に対してあまりにも鈍感であるという点で共通しているでも、継母の鈍感さは暴力であり、太一の鈍感さは不条理な世界を突破する救いである。
この継母と太一の違いを決定づけるものはなんなんだろうと考えながら期末試験の勉強をしています。
人種は交換可能?/“Your Face in Mine” (Jess Row)を読む (1)
ジェス•ロウが書いた、“Your Face in Mine”という本がある。
2014年夏に発売されたこの本は、そのセンセーショナルさからアメリカ国内ではかなり話題になったよう。人種問題への関心が高くはないからかどうかはわからないけれど、日本ではまだ有名じゃないみたい。和訳は出版されていないし、日本語でネット検索をしてもなかなか情報を得ることもできなかったもの。
これは秋学期の授業で扱った本。
アメリカで覇権を握りつつあるポスト人種主義への風刺が込められた作品。
とても内容が面白かったのでここに書こうと思う。
ストーリー
In the weak light of a February afternoon, Kelly Thorndike has a strange chance encounter in a Baltimore parking lot with Martin Lipkin, an old friend from high school. But time has brought a big change. The Martin that Kelly knew was white. The man standing before him is black.
Their meeting sets the stage for “Your Face in Mine,”Jess Row’s debut novel, which is to be published on Thursday by Riverhead Books, joining a long tradition of fiction about racial guises. Mr. Row’s tale is set in a near future in which Martin is the first person to undergo “racial reassignment surgery” to change his features, skin color, hair texture and even his voice. His surgical package includes a new biography and even a dialect coach — all a corrective for Martin’s “racial dysphoria.”
(Jess Row’s ‘Your Face in Mine’ Explores ‘Racial Reassignment’/ New York Times)
中国人の妻と娘を亡くし、失意の中毎日をすごしていたケリーが、故郷であるバルティモアに帰ったところから小説ははじまる。
ふるさとの街を歩いていると、道路の向こう側からこちらへ歩いてくる見知らぬ黒人の顔に、強烈なデジャヴを覚える。それもそのはず、その黒人の男性は、かつて白人だったはずの高校時代の同級生、マーティンが変身した姿だったのだ。
戸惑いを隠せないケリーに、マーティンは自身が「”人種”同一性障害」に陥っていたこと、そして「”人種”適合手術」を受けたことを告白する。「黒人になった」マーティンは、黒人起業家の地位を向上させるためのプロジェクトの一環として彼自身の半生を出版する計画を明かし、ケリーにその代筆の仕事をもちかける、というのがおおすじ。
ケリーはハーバード大学で中国思想を専攻し、英語を教えていた中国人女性ワンディと結婚をし、ときおり漢詩を引用するような、根っからの「中国かぶれ」な男性である。人一倍の思慮深さと、ナイーブさをもつ彼は、死別した妻ワンディにも「あなたはアメリカ人らしくない」と言われ、ワンディの中国の実家で過ごした日々を頻繁に思い出し、彼の人生の中で一番の幸せな時期だったと振り返る。この彼の中国文化への執着、そして中国文化への親近感に関する描写は、後の展開の布石となっているわけだけれど。妻と娘との、交通事故による死別、そして失業を経験した彼は、無気力に毎日をやりすごしている。
マーティンは根っからの「起業家精神」の持ち主として描写されている。ビジネストークにこの上なく長けている彼は、どんな人にもフレンドリーに接し、そしていつのまにか自分の計画に巻き込んでいるような男だ。自信に満ちあふれ、ブランドもののスーツを着こなし、街を堂々と歩く黒人のマーティン。ケリーは彼の記憶の中にある、消えてしまいそうな、生気のない、細い体つきの白人青年だったマーティンと現在のマーティンを一致させることができない。
ストーリーの前半は、ケリーがマーティンの半生を取材する中で、知らなかったマーティンの過去、そして彼が「人種適合手術」を受けるまでの経緯をときあかしていくという構成。
後半には、マーティンの本当の意図、すなわち「人種適合手術」を世界中の顧客に提供するサービスをビジネスにする計画、そしてそのケリーをそのビジネス拡大のためのモニターにする(白人からアジア人になる整形手術をする)ことこそがケリーに近づいた理由であることが明かされる。
ポスト人種主義について
ポスト人種主義とは、過去の市民運動により人種平等は「完全に」成立し、人種の差を意識するようなすべての政策や議論を不必要かつ好ましくないとする考えの系統をいう。近年のアメリカ社会はこのポスト人種主義の傾向を見せているとする政治学者もおおい。
しかしながら、人種的マイノリティは、政治/経済/社会制度が合わさって生み出す構造的な人種差別によって雇用機会、財産、生活のクオリティ、法の施行など多くのめんでライフチャンスを剥奪されているのが現実である。
ポスト人種主義は色盲主義(Color-blindness)、white-normativity(白人を規範とする考え方)の論理を使い、構造的な人種差別を覆い隠し、そして現状の力関係を維持をする。
この “Your Face in Mine”は、ポスト人種主義が包含するいくつかの要素を描いている。優位にたつ白人の人種不平等がはびこる現実への態度、色盲主義、そしてポスト人種主義とネオリベラリズムの共犯関係等々。
色盲主義について
色盲主義は、人種の違いを肌の色の違い「でしかない」と認識するものである。ある人種がもつ抑圧の歴史やステレオタイプによる被害などはすべて無視してしまう。これはつまり白人と非白人は政治的/経済的/社会的に対等な立場にあり、ヒエラルキーがいっさい存在しないととらえる。だからこそ色盲主義は、人種不平等を改善するためのアファーマティブアクションを含めた、人種によって違いがあるという考えのすべてを否定する。
色盲主義は、現在存在する人種の不平等を、すべて個人の問題であるとする「自己責任論」、抽象的自由主義、人種差別の極小化、そして文化的人種主義を用い、有色人種の社会的地位を、彼ら自身の問題であるとすることで、社会の構造的な問題を覆い隠してしまうのだ。抽象的自由主義は人種に関係する問題を自由主義の教義を用いて解釈することで、すべての人間に対して「平等な機会提供」を訴え、人種不平等是正を意識した政策を否定する。人種差別の極小化は、人種の不平等の問題が、人種差別以外のすべての要因から生まれたものとする。そして、文化的人種主義は、人種差別ではなく、有色人種のもつ文化や習慣こそが人種の格差を生み出していると考えるのだ。
white-normativityについて
white-normativityは、日本では日本人至上主義と言い換えられるかもしれない。色盲主義の社会では、白人のアメリカ人が特権を持ち、人生の様々な局面で優位にたつことができる。white-normativityは、「白人らしさ」が規範であり理想の姿であると定義することで、黒人の人々に黒人らしさを捨て、白人の規範を抱くことで「白人」に近づくことを推奨する。white-normativityも、現実に存在する格差と、それを生み出す社会の構造的問題を覆い隠すのに一役買っている。
メディアについて
メディアはポスト人種主義的社会を分析するためにも有用なツールだ。ロペスは「多人種的な個人」そして「人種の超越」というふたつの要素を取り出し、分析を行っている。ポスト人種主義は白人⇆黒人、アジア系⇆白人など、人種を切り替えることができる「多人種的な個人」(いわゆるハーフやクオーターなど、さまざまな人種の要素を持っている人のことをいう)を讃える。彼らは白人と非白人の仲介者であり、そして人種平等が達成されたというファンタジーを表す存在である。オバマはその「多人種的な個人」の一人である。そのような個人は、有色人種としてはその有色人種向けのニッチな市場にアクセスすることができるし(黒人らしさを主張したビヨンセ)、多人種としてはすべての市場にアクセスすることができる(セクシーでうつくしいビヨンセはアメリカ全体で大人気である)。
そしてメディアは「人種の超越体験」を幾度となく描いている。America's New Top Modelという人気ワイドショー番組はその代表。
このショーでは、メイクや衣装によってヨーロッパ系アメリカ人女性が中国人の女性になったり、アフリカ系の女性が北欧の女性に変身したりする。この人種パフォーマンスは、ファッションやコスメ商品を使いさえすれば、人種を「交換可能」なものであるととらえているのだ。そしてその変身の過程には「ステレオタイプ」が欠かせない。人種の超越には、その変身する人種の記号的な象徴を配置することが不可欠だからだ。たとえば日本人の女性になるときは、真っ赤な民族衣装を着て、目をつり上げる。アフリカ系の女性になるときは、肌を黒く塗り、「アフリカっぽい」民族衣装を着て、アフロのかつらをかぶり、子どもと一緒にうつる、みたいに。
時間ができたら小説がどうポスト人種主義の理論を批判しているかということについて書きます。(書き終えたのに消えてしまったので泣きたいです。)
ホームシックをなおしてくれた本たち
どうやらわたしはホームシックにかかってしまったみたい。
日本の生活の中にあった、形容するのが難しいあの雰囲気をとてつもなく恋しく思っている。日本に帰りたいとは思わない。だって、帰ったとしても、私はきっとまた別の居場所を探そうとするだろうから。ボーヴォワールがいうように、場所をうつしさえすればもっと幸福になれるだろう、とわたしたちは思ってしまいがちだけど、本当は場所じゃなくて、その人のこころもちこそが大切なのだ。
人生とは、病院のようなものだ。そこでは患者それぞれがベッドの位置を変えたい欲望にとらわれている。この者は、どうせ苦しむなら暖炉の前でと望み、かの者は、窓際なら病気がよくなるだろうと信じている。
私もまた常に、どこか違う場所ならもっといいに違いないと感じている。場所を移すということは、私がいつも自分の魂に問いかけているテーマなのだ。
「いってごらん、我が魂よ、冷たくなってしまった哀れな魂よ、リスボンで住むのはどう思う?あそこは暖かいだろうし、きっとトカゲのように元気を取り戻せるさ。この街は海辺にあるんだ。建物は大理石で作られ、住民は野菜が嫌いなので木という木を引き抜いてしまうということだ。お前の好みに合っているし、光と鉱物と水で作られ、人々を元気にしてくれるんだ。」
我が魂は答えない。
「お前は動くものを眺めながら休息するのが好きだから、オランダに住むのはどうだろう、あの至福に包まれた土地で?お前は美術館で絵を見るのが好きだから、きっと気晴らしになるさ。ロッテルダムをどう思う?お前は人家の近くに係留している船の帆を見るのが好きだろう?」
我が魂は無言のまま。
「バタビアのほうがもっといいかもしれない。熱帯の美と結婚したヨーロッパの精神がそこにはあるから。」
何の言葉も返ってこない。我が魂は死んでしまったのだろうか。
「お前はとうとう、災いにしか楽しみを感じないほど麻痺してしまったのか。もしそうなら、死のアナロジーであるような国へ行こう。始末は私がするから、荷物をまとめてトルネオに旅立とう。いやもっと遠くへ、バルト海の果てまで行こう。出来ることなら、日常の生活からはるかに離れて。そうだ北極に住もう。そこの太陽は斜めにしか地面を照らすことなく、昼と夜がゆるやかに交代するおかげで、変化がなく、単調そのものだ。まさに死の片割れのようなところ。我々はそこでゆったりと闇につかり、北極のオーロラは我々を楽しませるために時折、地獄の花火が反射したようなばら色の花束を贈ってくれるだろう。」
ついに我が魂は爆発し、さかしくもこう叫んだ。
「どこでもよい!この世の外であるならば、どこでもよい!」
(N'importe où hors du monde/ ボードレール)
ただ、ぼんやりと、日本の生活をなつかしく、恋しく思っているだけ。帰る場所があるという淡い期待を抱ける、この恋しく思っている状態がもしかしたらいちばんよいのかもしれない。
この大学での生活は楽しい。仲の良い友人もいるし、お気に入りのレストランもあるし、なかなか美味しいお寿司を食べれる店だってある。授業の内容もぜんぶわかるし、日常のどうでもよいような会話をかわすこともする。日本の友達が恋しくなればスカイプできるし、フェイスブックをみればみんながなにをしているかはなんとなく想像できる。映画はいっぱい見れるし、本も読めるし・・・。
でも、どうしてもこの世界になじめない、空虚感をいだいている自分がいるのだ。ここは日本でないからかもしれないし、もしくは私が育った母国でないからなのかもしれない。だから、わたしがなじむことができる、なじむことをだれからもゆるされていると思える世界に身を置きたいと思っている。それがホームシックの感情をおこしている、のかも。
なじめない、とおもうのは、ここでの毎日の質感が、私が慣れ親しんだ日本のそれと大きく違っているから。たとえば、テレビで流れる流行歌や、広告の配色やそのデザインや、アメリカ人の表情の作り方が、わたしにとってはなじみがないもの。そのを一種の系統として認識してしまう。黄色人種の顔の特徴に目がいってしまって、それぞれの顔を区別できない他人種ようなものだ。その表層の違い、スタイルの違いがいやに目について、その内容まで心が入り込めない。何を示しているかはわかる。ただそれがどのような位置にあるのかを判断することが出来ない。
その「入り込めなさ」に、息苦しさと違和感を感じてしまって、なにかもっと入り込めるもの、そしてわたしに入り込んでくれるものにすがりたいという感覚を覚えている。自分は疎外されているし(疎外ということばの調子はつよいけれど、これ以外に適切なことばが思いつかなかった)わたし自身もここにあるものをどこか疎外してしまっている。自分が「他者」であることをとことん思い知らされる。
ひらがなの曲線、文字だらけのネオンライトの街、大きなピンクリボンのついたダサいエナメルバッグ(サマンサタバサのかっこわるいピンクのバッグ)、みたいなものたちが作り出す、スピッツやミスチルの曲が生まれえるあの雰囲気、あの洗練されていない「と思える」雰囲気を、とても懐かしく思う。
図書館で見つけた日本語の本たちを、いっきにぐぐっと摂取したら気分がだいぶ楽になった。考えてみれば11年前のノースカロライナ以来でこんなに海外に滞在するのははじめてだし、一人暮らしもはじめての経験なので、こういうふうになるのも当然なことだ。この感じは、ちょっといやだけど、こんな気分を経験できるのも留学の良さだなあと思っている。
本を読むと、自分の人生が多くの人生のたったひとつでしかないということを実感できて、すこしほっとする。それに、小説家の表現や視点を借りてみることで、自分の人生に対してもっと客観的になれる気がする。なやんでいることは、たいしたことないじゃないか、と思える。だからいものがたりといつもいっしょに暮らしていたい、と思う。
この土日で読んだのは以下のとおり。
「何者」を読んでいる時、心臓がずっとどきどきしていた。クリスティの「春とともに君を離れ」と同じ鋭さ。これのおかげでホームシックはほとんど消え去ってしまった。甘いことをいってるんじゃない、どこでも、日本であっても、いつも息苦しさを感じていただろう、と思い出させられているようで、これからもこのままじゃ息苦しい人生が待っているよ、といわれているようでもあって。いろんなことに文句を抱いてしまいがちな私だけれど、その度にこの本を思い出そうと思う。
そして、眩しいくらいにまっすぐで健康な心根をしている友人たちを、もっと大切にしなければと思いました。だってそういう人たちといっしょにいれば、彼らの論理が正しい世界がわたしのまわりに広がるから、わたしもそんな人間の一人になれる気がしそうだもの。
いつか詳しい感想を書きたい。
とてもびっくりした。こんなに素晴らしい本を読まずにいたなんて残念だ。「自意識の病」にかかってしまったひと、そして社会に違和感を抱いてしまった人すべてに「ぴん」とくる話だろう。予定調和の世界から逃避できるのか。という話。もう一度読む。
セックスに必然性が感じられない調子はあいかわらずだけど、ものがたりがドラマチックでおもしろくていつもみたいに細部のディテールが気にならない。
ライトノベル風の文章の調子に慣れるのにずいぶんな時間がかかった。表現は独創的だけど、あまりきれいだとはおもえなかった。
ディストピアの話で、オーウェルの1984の系譜を継承しつつ、現代の問題をおりまぜつつ、ライトノベルの調子をまじえているようなお話。斎藤純一先生の公共哲学の授業を思い出しながら読んでいました。物語をすすめるために歴史の事象をやら国際関係やらを使っていたのだけれど、そのあつかいかたが粗雑だったのが悪印象でした。
本を読んだらとても元気になったので、今週もリラックスしつつ頑張ろうと思う。
グローバリゼーションのもとに輝くインド/"City Dwellers: Contemporary Art from India" (Seattle Art Museum)
グローバル化の流れがあらゆる国の文化にも多大な影響をおよぼしているのは周知のこと。
豊潤な文化をもつインドもその例外ではなく、グローバル化がつれてきた資本主義システムと消費社会はその文化に大きな変容をもたらしている。
わたしたちがインド文化と聞いて思い浮かべるような、サリー、ヒンドゥー教の神々の像、カレーやナンみたいにステレオティピカルなものたちだって、グローバル化の影響を受けて違うかたちを見せるようになってきているのだ。シアトル美術館(Seattle Art Museum) の3階で行われている"City Dwellers: Contemporary Art from India" は、現代インド社会への新たな視点をわたしたちに与えてくれる。

長い廊下の壁に沿って、Dhruv Malhotraの写真の連作、"Sleepers"がかけられている。地面で寝ている人もいれば、自転車タクシーで、がれきの中で寝ている人だっている。寝ている場所、そしてその色彩があまりにふつうでないので、フィクションであるように感じてしまうけれど、これは実際にMalhotraが外で眠るさまざまな姿を彼のカメラにおさめたものなのである。

Sleepers/ Dhruv Malhotra
いくつかの眠りにふける姿たちの中で特にわたしの関心をひいたのは、ベンチで丸まって眠る男の写真。不自然なくらいに鮮やかな緑の芝生、不気味なくらい赤い空と荒廃した建物の姿は、まるで悪夢の中にでてくるシーンのようだ。彼は洋服以外になにもまとっていない。彼の眠りを邪魔してしまいそうに色鮮やかな世界の中で、男はまるで敵対する世界から自分を守るように、小さく、かたく丸まってベンチの上で眠っている。この構図は昔みた、現実から(酒の力を借りて)逃げるように身体を丸める女性を描いたピカソの"Abinsthe Drinker"を連想させる。

Abinsthe Drinker/パブロ・ピカソ
眠る男は暗闇にとけ込み、目覚めることを拒否するように、きびしい現実から逃げるように、こんこんと眠りに耽っている。 写真は絵画よりも現実を捉えるのに適している、とよく考えられているものだけれど、もちろん現実を正確に捉えることはできない。光や色はレンズや印刷によって変わるし、構図はアーティストの感性に強く影響されるからだ。つまり、アートとしての写真は、アーティストの意図を反映しつつ、かつ「より現実的である」という説得力も有している。アートとしての写真こそが、現実のゆがみを指摘するのに最も適している手法であるのかもしれない。
インド経済は急速な速さで成長をしているけれど、その一方で、格差も拡大している。少数の裕福な人びとがその経済成長の恩恵を独占し、その他の大勢は貧困のもとに生きることを強いられている。Malhotraの非現実的な、しかし息をのむほどうつくしい写真の連作は、インド社会が直面する問題をうつくしく、そしてシニカルに捉えている。
"Sleepers"が飾られた廊下を抜けると、この展覧会で一番大きな部屋がある。まずはじめに目に飛び込んでくるのは真っ赤に輝く、等身大サイズのモハメド・ガンディー像。精密に再現されたガンディーは、トレードマークである杖をひきながら、真っ白なiPodで音楽を聞きながら歩いている。

India Shining / Debanjan Roy
鮮烈な赤は、不快感さえ催させる。私たちが歴史の教科書で見たままの<慈悲深い>はずの笑顔も、その強烈な赤色によって、攻撃的な、嘲笑しているかのようなな表情に見えてしまう。真っ赤に塗られたガンディーは、CMにでてくるようなポップアイコンに変化している。そしてアルミニウムでできている、ガンディー像の材質感はいやにキッチュで、まるで大量生産品のおもちゃのようなチープさを醸し出している。
この色と材質のセレクトこそが、この作品にこめられた風刺のメッセージを成立させているのだろう。イギリスからの独立のシンボルである「建国の父」ガンディーが、消費文化・グローバリゼーションのシンボルともいえるiPodに夢中になっている様子は、イギリスの次の支配者である消費文化と・グローバリゼーションを喜んで受け入れるインド社会への鋭い風刺なのだ。
この像のタイトル"India Shining"は2004年の選挙のためにBJPが掲げたメッセージ。インドの経済成長と明るい未来を讃えるこのスローガンを、このガンディーにつけるなんて、なんともアイロニーに満ちている。
大きな部屋の隅には、Native Women of South India: Manners and Customs (Pushpamala N and Clare ARni)が架かっている。

Native Women of South India: Manners and Customs /Pushpamala N and Clare ARni
どこの文化のものかは特定できないけれど、典型的にエキゾチックなデザインの伝統衣装に身を包んだ女性が、ギンガムチェック柄の壁紙の前に立っている写真。おそらく民俗学の研究が行われているのだろう。女性はまるでプレパラートに固定された植物のような、もしくはピンでとめられた蝶のように器具にその腕を置き、観察をされている。彼女は反抗的な目でカメラ=観察者をまっすぐ見据えている。その写真を鑑賞している、観察者の立場であるわたしたちは、まるで自分が非難されているかのような感覚を覚えるだろう。これはかの有名なマネのオリンピアと同じ構図。

Olympia / エデュアール・マネ
こちらに向けられたまなざしは、観察者をそのコンフォートゾーン、第三者的立場から無理矢理ひっぱりだし、<見る者>から<見られる者>に対する優位性・支配性を剥奪し、確実に存在する関係性をあらわにする。
この女性は実際にこの写真作品を制作したアーティストで、写真の中でおこるすべてはパフォーマンスなのだ。<ネイティブ>の女性は、性差別・人種差別、そしてステレオタイプに抑圧されてきた。<ネイティブ>としては支配的なグループへの従属を強いられ、西洋人からの好奇の目にさらされてきたし、<女性>としては男性への従属を強いられ、彼らの欲望のまなざしに支配されてきた。
彼女のパフォーマンスは、現代に存在する支配関係をあらわにする。そして彼女のまっすぐなまなざしは、そのステータス・クオーに小さな切り込みを入れるものなのだろう。
この作品はモノクロ。色がないというコンディションは、その作品の時代性を消し去る。50年前にとられた写真かもしれないし、今年とられた写真かもしれない。モノクロであることは作品に永遠性をあたえ、わたしたちが今の時代と無関係だと捨て去ってしまうことを防ぐ効果があるかもしれないなあなんておもったり。
シアトルにはこの展覧会が開催されていたSeattle Art Museum (SAM)と、そのほかにSeattle Asian Art Museum (SAAM)がある。この展示がSAAMでなくSAMで開催されたということにはとくべつな理由があるにちがいない。それはきっとこの展覧会がインド社会を超えたなにかをあらわしているからだ。消費文化とグローバリゼーションと密接に関係した現代化の、恩恵と弊害をあらわした作品たちは、いまわたしたちがいる現代社会についてもういちど考えることを促している。まあきっとこの消費文化とグローバリゼーションというものは、局地的な、たとえばアジアだけでおこっていることではないので、こっちのSAMでひらかれたのかもしれないね。







